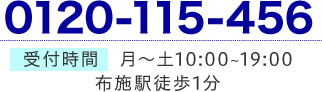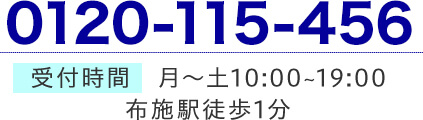交通事故で腰や背中の骨のうち、脊椎や腰椎を圧迫骨折し、その症状が重い場合は治療してもしびれや痛みなどの後遺症が残ります。この場合は、6級、8級、11級、12級、14級のいずれかの後遺障害認定を受けられ、等級に応じた慰謝料請求が可能です。圧迫骨折による後遺障害認定と弁護士へ相談すべきかについて解説します。
交通事故による圧迫骨折は後遺障害認定を受けられる? 慰謝料の金額や注意点を解説
交通事故で強い衝撃を受けた場合は、腰や背中の骨のうち、椎体を圧迫骨折してしまうことがあります。圧迫骨折は2ヶ月から3ヶ月程度で治癒するのが一般的ですが、症状が重い場合は後遺障害が残ってしまうこともあります。
圧迫骨折で後遺障害となった場合は、6級、8級、11級、12級、14級のいずれかに該当するため、適切な慰謝料請求や損害賠償請求を行いましょう。
圧迫骨折とは?
交通事故で身体に強い衝撃を受けた時は、骨折してしまうことがあります。
骨折というと足や腕の骨がポッキリ折れるイメージがあるかもしれませんが、骨が潰れる形の骨折が発生することもあります。
圧迫骨折はその代表例です。
圧迫骨折は、腰や背中の骨のうち、脊椎や腰椎等の椎体という部位が潰れてしまう形の骨折のことです。
高齢者や閉経後の女性等で骨粗鬆症を患っていると、尻餅をついただけで、潰れてしまうこともあります。また、事故とは関係なく体の重みを支えきれなくなって、いつの間にか潰れていることもあるようです。
交通事故で強い衝撃を受けた場合は、高齢者でなくても、圧迫骨折を発症してしまうおそれがあります。
圧迫骨折の例
圧迫骨折は、身体のどの部位の骨が潰れているのかにより、
- ・腰椎圧迫骨折
- ・胸椎圧迫骨折
- ・頚椎圧迫骨折
の3つに分類できます。
圧迫骨折してしまうと、しゃがんだり起き上がったりといった動作をする際に、腰、背骨、首の後ろ等に強い痛みを感じてしまいます。
最悪の場合は、介護が必要な状態になってしまうため、楽観視することはできません。
交通事故後に圧迫骨折と診断されたら、しっかりと治療することが大切です。
圧迫骨折の診断方法
圧迫骨折の診断は、レントゲン、MRI、CTの画像により行います。
レントゲンでは、骨折による椎体変形を確認します。ただこれだけでは、新しい骨折なのかすでに治って変形しているだけなのかが分かりません。
交通事故の場合で言えば、事故による圧迫骨折なのか、事故とは関係なしにもともと圧迫骨折していたのかが分からないということです。
MRIを撮ることで新しい骨折なのかどうかが明らかになります。
さらに、CTによってどのような治療方法を採るべきか検討することになります。
圧迫骨折による後遺障害認定を受ける場合も、こうした画像による診断が重要になります。
圧迫骨折の治療方法
圧迫骨折の治療方法としては、痛み止めを飲んで安静にすることやコルセットを装着することで骨癒合を待つといった保存療法が一般的です。
ただ、骨折の程度が重い場合は、様々な手術療法も行われます。
- ・骨セメント(人工骨)を骨折部に注入・充填する経皮的椎体形成術(BKP)
- ・金属製のスクリューを骨折部にはめる脊椎後方固定術
などが代表的です。
圧迫骨折の治療が終わるまでは、日常生活でも様々な動作が厳禁されます。
例えば、
- ・前かがみになる
- ・重いものを持つ
- ・体を捻る動作
- ・無理なストレッチ
- ・背骨に負担のかからない寝具を選ぶ
といったようなことです。
しっかり治療を行わないと、偽関節といい、骨がくっつかないままで完治しない状態になってしまうので注意しましょう。
交通事故による圧迫骨折が症状固定となる目安は?
椎体圧迫骨折は、一般的には2〜3ヶ月で治ると言われています。
医師の指示に従って、日常生活で様々な動作を行う際に気をつけていれば、比較的治りやすいと言えるでしょう。
しかし、圧迫骨折の程度が重い場合は、完治せず痛みが残ってしまうこともあります。
交通事故でケガを負って治療を開始したものの6ヶ月経過しても完治しない場合は、これ以上治療しても完治しないものとされて症状固定となることもあります。
交通事故後6ヶ月経過しても治療を続けている場合に、相手方の任意保険会社から、症状固定の打診がなされることもあります。
ただ、症状固定を最終的に判断するのは主治医です。
医師が治療を続ける必要があると診断している場合は、保険会社からの申し出を断り、治療を続けることが大切です。
圧迫骨折が症状固定となったら後遺障害等級認定を検討する
圧迫骨折が完治せず、症状固定となってしまった場合は、日常生活のあらゆる動作で、腰、背骨、首の後ろ等に強い痛みを感じるようになってしまいます。
その結果、仕事に支障が出たり、今までの仕事ができなくなることもあります。
このように、圧迫骨折が症状固定となったことで、仕事に支障が生じている場合は、後遺障害等級認定の申請を検討すべきです。
※後遺障害とは
交通事故が原因で後遺症が残ったことで、労働能力の低下や喪失が認められ、その程度が自賠責保険の後遺障害等級に該当する場合のことです。
後遺障害等級認定を受けることにより、後遺障害慰謝料や逸失利益といった損害賠償金の支払いを加害者側に求めることができます。
圧迫骨折による後遺障害等級の認定基準
圧迫骨折による後遺障害は、
- ・変形障害
- ・運動障害
- ・荷重機能障害
- ・神経症状
のいずれかに該当することが多いです。
圧迫骨折による変形障害
圧迫骨折によって脊柱の変形が残ったままとなり、症状固定になった場合です。
側彎(側弯症)と呼ばれる症状になり、背骨が曲がった状態になります。
その結果、次のような症状が生じます。
| 外見上の異常 | 背部や腰部の突出や肩の高さの左右差が生じる等です。 |
|---|---|
| 痛み | 変形していることにより、背中や腰に痛みやこりが生じやすくなります。 |
| 神経症状 | 変形が大きい場合、脊髄が障害され、脊髄麻痺が生じることがあります。 |
| 呼吸器症状 | 胸郭が変形することで肺活量が減少し、息切れしやすくなることがあります。 |
こうした症状により、労働能力の低下や喪失が認められる場合は、変形の程度により、下記の後遺障害等級のいずれかに該当する可能性があります。
| 6級5号 | 脊柱に著しい変形を残すもの |
|---|---|
| 8級相当 | 脊柱に中程度の変形を残すもの |
| 11級7号 | 脊柱に変形を残すもの |
圧迫骨折による運動障害
圧迫骨折した部位に強直、可動域制限が生じた結果、頸部または胸腰部を動かしづらくなり、そのまま、症状固定となった場合です。
運動障害が生じると、日常生活の様々な動作に支障が生じるようになります。
運動障害が残った結果、労働能力の低下や喪失が認められる場合は、その程度により、下記の後遺障害等級のいずれかに該当する可能性があります。
| 6級5号 | 脊柱に著しい運動障害を残すもの |
|---|---|
| 8級2号 | 脊柱に運動障害を残すもの |
圧迫骨折による荷重機能障害
脊椎は、人体の頭や胴体を支える重要な役割を果たしていますが、圧迫骨折によってその機能が削がれた場合は、硬性補装具が必要になります。
こうした状態になると、日常生活の様々な動作に支障が生じることはもちろんのこと、労働能力の低下や喪失にも繋がります。
その程度により、下記の後遺障害等級のいずれかに該当する可能性があります。
| 6級相当 | 頸部及び腰部の両方の保持に困難があり、常に硬性補装具を必要とするもの |
|---|---|
| 8級相当 | 頸部又は腰部のいずれかの保持に困難があり、常に硬性補装具を必要とするもの |
圧迫骨折による神経症状
圧迫骨折すると、腰、背骨、首の後ろに強い痛みやしびれ等を感じるようになります。
完治に向かうに従い、痛みやしびれ等は和らぎますが症状が続いたまま症状固定となる場合です。
痛みやしびれのために、労働能力の低下や喪失が生じている場合は、その程度により、下記の後遺障害等級のいずれかに該当する可能性があります。
| 12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
|---|---|
| 14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
交通事故の圧迫骨折で請求できる損害賠償金の費目
交通事故で圧迫骨折の被害を受けた人が請求できる損害賠償金は、後遺障害等級認定を受ける前に請求できる費目と認定を受けた後で請求できる費目に分けられます。
後遺障害等級認定を受ける前でも請求できる費目
後遺障害等級認定を受ける前でも請求できる賠償金の費目は次のとおりです。
| 治療費 | 治療にかかった費用のことです。 |
|---|---|
| 休業損害 | 入院や通院のために仕事を休んだ事による損害です。 |
| 入通院交通費 | 入院や通院のためにかかった公共機関の交通費などです。 |
| 入通院(傷害)慰謝料 | 交通事故の被害者となったことで精神的苦痛を被ったことについて金銭的な償いを求めるものです。 |
このうち、入通院(傷害)慰謝料は、自賠責基準、任意保険基準、裁判基準(弁護士基準)のいずれかの基準で計算します。
自賠責基準は、自賠責保険法で定められた最低限の補償額です。
任意保険基準は、自賠責基準をベースに上乗せするもので、任意保険会社が独自に決めていますが、微増にとどまることも多いです。
これらの2つの基準で計算した金額では納得できない被害者も少なくないと思います。
裁判基準(弁護士基準)は交通事故の裁判で認められた基準で、3つの基準の中で最も高額になります。
適切な慰謝料を請求するためには弁護士に相談、依頼することが大切です。
後遺障害等級認定を受けた後で請求できる費目
後遺障害等級認定を受けることで、上記の費目に加えて、以下の費目の賠償金も請求できるようになります。
- ・後遺障害慰謝料
- ・逸失利益
- ・家屋のリフォーム費用など
後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料は、後遺障害に該当するほどの障害が残ったことで被害者が精神的苦痛を被ったことについて金銭的な補償を求めるものです。
1級から14級までの後遺障害等級ごとに金額が異なっており、1級ほど金額が高くなります。
後遺障害慰謝料も、自賠責基準、任意保険基準、裁判基準(弁護士基準)の3つがあり、裁判基準(弁護士基準)が最も高額になるのが一般的です。
圧迫骨折による後遺障害慰謝料について自賠責基準と裁判基準(弁護士基準)の金額をまとめておきます。
| 後遺障害等級 | 自賠責基準 | 裁判基準(弁護士基準) |
|---|---|---|
| 6級 | 512万円 | 1,180万円 |
| 8級 | 331万円 | 830万円 |
| 11級 | 136万円 | 420万円 |
| 12級 | 94万円 | 290万円 |
| 14級 | 32万円 | 110万円 |
逸失利益
交通事故により圧迫骨折の後遺障害が残ったことで、労働能力の低下や喪失が生じると収入が減ります。
交通事故で圧迫骨折の後遺障害にならなければ、減った分の収入を得られていたはずです。
この得られたはずの収入のことを逸失利益と言い、被害者から加害者に請求できます。
逸失利益の計算式は次のとおりです。
基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数
このうち、労働能力喪失率は、後遺障害等級ごとに次のような目安が用意されています。
| 後遺障害等級 | 労働能力喪失率 |
|---|---|
| 6級 | 67% |
| 8級 | 45% |
| 11級 | 20% |
| 12級 | 14% |
| 14級 | 5% |
逸失利益は、加害者側の保険会社と示談交渉を行う際に争点となりやすい費目です。
加害者側の保険会社は、圧迫骨折による変形障害は認められても、労働能力の喪失を伴うほどのものではないので、逸失利益はない、または減額すべきといった主張をすることが多いです。
このような場合は、今までできていた仕事ができなくなったとか、収入が減った事実を示す等により、争うことも検討すべきです。
加害者側の保険会社がこうした主張をしている場合は、早めに弁護士にご相談ください。
交通事故の圧迫骨折の示談交渉で注意したいこと
交通事故の圧迫骨折では、加害者側の任意保険会社が次のような主張をすることがあります。
- ・交通事故と圧迫骨折との因果関係を否定する。
- ・被害者の身体的特徴や既往症による素因減額を主張する。
簡単に言うと、
- ・交通事故前から、骨粗鬆症などが原因で圧迫骨折が生じていた。
- ・交通事故で圧迫骨折したのは、被害者が骨粗鬆症を患っていたからだ。
といった主張がなされてしまい、保険金や損害賠償金を受け取れなくなってしまう事態が考えられます。
このような場合には、病院でMRI、CTの画像による診断を受けて、交通事故によるものであるかどうか精密に検査してもらうとともに、弁護士にも相談し加害者側の主張に対して的確な反論を行う必要があります。
まとめ
交通事故で圧迫骨折のケガを負ってしまった場合は、まず、主治医の指示に従って、適切な治療を受けることが大切です。
圧迫骨折が完治せず、症状固定となった場合は、後遺障害等級認定の申請も検討しましょう。
圧迫骨折は、交通事故とは無関係に発症していることもあるため、因果関係が否定されることもあります。
加害者側の主張に納得できない場合は、早めに弁護士に相談することが大切です。